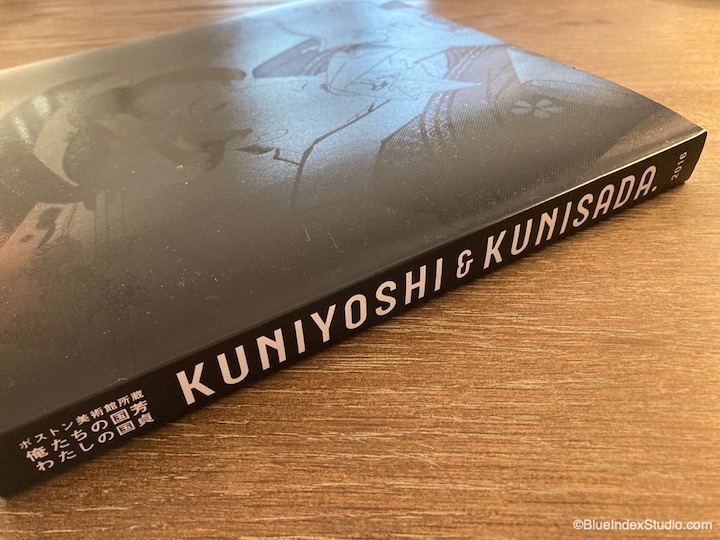ボストン美術館(MFA)で、同館所蔵のターナー作品として唯一公開されているのが《奴隷船》(2022年12月現在)だ。

MFA Accession# 99.22
光と色の混合に燃えるような筆致。それらが醸し出す靄のかかった画面は遠くからでも一目でターナーの作品とわかる。左右に異なる表情を見せる空と前面に盛んに荒れ狂う海の境目は、黄色と赤褐色の燃え立つ炎と沈みゆく太陽の交わりが劇的な風景を描き出している。そんな激動する水面に、夕方の日差しに染まる難破船が頼りなげに漂っています。手前には、波に抗する魚の群れと海に放り出された奴隷たち。自然の猛威の前では人間の力など及びようもない。
この作品は、海難事故の保険金目当てに船上の病人や死人を海に放り出したイギリス船の実話を元にした18世紀の詩にインスピレーションを得て描かれたそうだ。1840年にロイヤルアカデミーで公開され、その際にはターナーの未完成で未公開の「Fallacies of Hope(偽りの希望)」(1812)という詩も添えられていた。
ところで、ターナーは1818年にイタリア旅行の機会を得る。多くの特に北ヨーロッパの芸術家が経験するイタリアの光の洗礼をターナーも受けたのだろう。つまり、この旅を契機に彼の画面の明度が高まった。そしてこのころから、モチーフは具象というよりもターナーが受けた「印象」のままに描かれていくのだ。1838年にはイギリス国民が愛してやまない絵画《戦艦テメレール号》、1840年の《奴隷船》、そして3年後の1843年にはゲーテの理論を表現した『光と色』が発表されている。フランス印象派の始まりとされるモネの《印象・日の出》(1872)からは約30年先をいった印象表現が行われていたのだ。
この作品の来歴について少し。
1843年ターナーの代人からの最初の購入者はジョン・ジェームス・ラスキンといい、息子ジョン・ラスキンのために購入した。ジョン・ラスキンは美術評論家として、コレクターとして、さらにラファエル前派の擁護者として、ヴィクトリア期のイギリス芸術には頻出する人物。ジョン自身若い頃からターナーとの交流があった。そしてこの作品を、ターナーを不朽たらしめる一作と評している。
1869年ラスキンは本作品《奴隷船》をロンドンで売却することに失敗し、1872年にニューヨークでアメリカ人に売却する。その後も数回のアメリカ国内での売買をへて1899年ボストン美術館が購入し現在に至っている。
ところでMFAではもう一作、個人蔵のターナー作品が展示されている。

右 Slave Ship(1840)MFA所蔵
この2点、制作年に数年の差があるが画面構成がとてもよく似ている。《Ancient Italy》はローマ帝国に思いをはせた詩にちなんだ作品とのことで、手前に描かれた水揚げした戦利品らしきものや武装した人々が非武装の男を移動させている様子などに戦いの時代が垣間見られる。一方で強い光が作り出した靄のベールに包まれた美しい都市景観や、船着き場に座って肩を寄せ合う女性たちの存在のせいか、どこか穏やかな時間の流れも感じられる作品だ。
<参考サイト>
Joseph Mallord William Turner《Slave Ship (Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On)》ボストン美術館
https://collections.mfa.org/objects/31102/slave-ship-slavers-throwing-overboard-the-dead-and-dying-t?ctx=b4e1dd76-f897-4ade-95aa-51a6d85b4e20&idx=0